「大事なプレゼンの前に必ずお腹が痛くなる…」
「緊張すると急にトイレに行きたくなる…」
こうした経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか?
実はこれ、気のせいではなく科学的に説明できる現象なんです。ポイントは「脳と腸のつながり」にあります。

■ 脳と腸を結ぶ“脳腸相関”
私たちの腸は「第二の脳」と呼ばれるほど神経ネットワークが発達しています。腸の神経細胞はなんと 約1億個。その腸と脳をつないでいるのが「迷走神経」という太い神経です。
この双方向のネットワークを 脳腸相関 と呼び、ストレスと消化器症状の関係を説明するカギとなります。
■ ストレスがかかると何が起きる?
強いストレスや不安を感じると、脳の「視床下部」が反応し、自律神経を通じて全身に信号を送ります。すると以下のような変化が起きます。
- 交感神経が優位になり、腸の蠕動運動が乱れる
- 消化液の分泌が減り、胃腸の機能が低下
- セロトニン(腸内で作られる幸せホルモン)の分泌バランスが崩れる
結果として、「下痢・腹痛・便秘」などの症状が出やすくなるのです。

■ 腸が“ストレスセンサー”になっている理由
実は腸には、体内のセロトニンの 約90% が存在しています。
セロトニンは気分の安定に関わるだけでなく、腸の動きを調整する役割も持っています。
ストレスでセロトニンが乱れると、腸は過敏に反応しやすくなります。これが「過敏性腸症候群(IBS)」の主な要因の一つです。

■ 改善のためにできること
脳と腸は一方通行ではなく、腸の状態が脳のストレス反応を和らげることも分かっています。
つまり「腸を整える」ことがストレス対策にもなるのです。
- 呼吸法や瞑想 → 自律神経を落ち着け、腸の緊張を緩和
- 適度な運動 → 腸の蠕動を促し、セロトニン分泌をサポート
- 腸にやさしい食事 → 発酵食品・食物繊維を取り入れて腸内環境を改善
- 十分な睡眠 → ホルモンバランスと腸の修復に不可欠
「脳を休める」ことと「腸を整える」ことを同時に意識すると、ストレスによるお腹の不調が和らぎやすくなります。
■ まとめ
ストレスでお腹を壊すのは、単なる体質ではなく「脳腸相関」という科学的な仕組みが背景にあります。
脳と腸は密接にコミュニケーションを取っており、心の緊張が腸に届いて不調として現れるのです。
だからこそ、心と体をバランスよく整えることが大切。
「お腹の調子が悪い=ストレスのサイン」と受け止め、日々のケアに役立ててみてください。











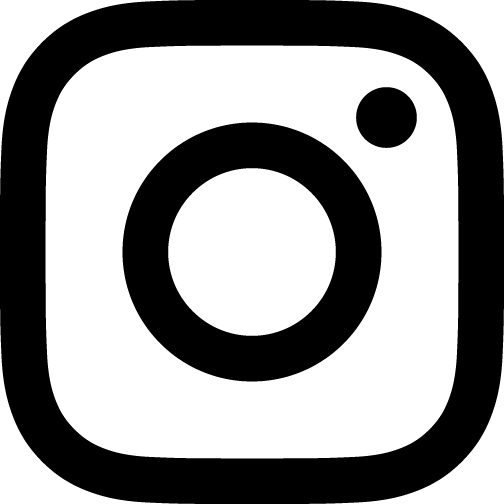
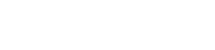



コメント